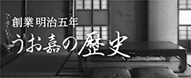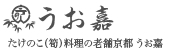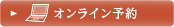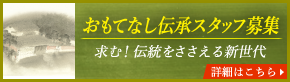2014年 05月 07日
5月のGWが終わりました。
このころから 竹の子も成長度合いをまして、
親竹もどんどんおおきくなります。
たけのこ自体も地下茎の深いところからでてくるので、筒状で繊維質の強い竹の子が多くなります。
そんな竹の子を「名残りの竹の子」と呼びます。
ところが、5月の朝夕の気温の低さと4月の雨の少なさで、
いまでも名残りどころか4月のころの旬の竹の子がでてきています。
農家の方も今年は「 盛り(旬)がおくれているでぇー」「今頃でもいいのが出よる。」と笑みを含んでおしゃります。

5月6日に大原野 小塩でとれた白子の筍です。
今年は竹の子ファンにいい5月になりそうです。
天候に感謝 竹林に感謝 農家に感謝
たけのこ大使 莞鳴
2014年 05月 05日
京都の方でも意外と知らないことが多くある。
また、食通の方でも産地の歴史はあまりご存知ない。
京都の竹の子の歴史について調べてみた。
京都の名産の竹の子は 「孟宗竹」(もうそたけ)と呼ばれ中国大陸からもたらされた外来種である。
このもたらされた経路には様々な諸説があり、専門家もいろいろ説をとり、いまだわからない謎です。
九州地方の学者は中国から琉球(沖縄)を通じて、薩摩藩から入ったといわれます。
しかし、京都の竹の子の歴史を探ると
山城国(現在の京都府南部)における孟宗竹の栽培は、徳川時代、享保19年(1734年)に綴喜(つづき)地域に始まり、
京都、西山地域(旧名:おとくに=乙訓)には寛政年間の1790年頃に移殖されたと記されております。
この地域に住む 朝田文次郎が、宇治・八幡方面から大枝長野新田と寺戸堺に植えたのが最初であるといわれています。
(「大枝・大原野の里」より 京都市開発局 発行)
ですので、薩摩藩からの移植より前にすでに孟宗竹が京都にあったと思われます。
また、宇治の黄檗山万福寺の僧が唐から持ち帰り、乙訓郡奥海印寺の寂照院に植えたともいわれます。この僧こそ、禅宗の曹洞宗で有名な
道元禅師だったともいわれたり、はたまた、その僧は弘法大師の空海の縁者だともいわれます。
どちらにしろ、この地の竹の子は孟宗竹がほとんどで
竹の子を農業収穫物として、江戸後期から栽培奨励されたようです。
そして、明治の中期以降、竹の子の栽培はいっそう盛んになり、大正時代には全国に京都の竹の子の名が知れるほどの産地になりました。
この地の自然環境や土壌が竹の子栽培に適していることもあり、良質の竹の子がたくさん収穫され、それが今も続いているのです。
もちろん、それを支えた 竹林農家の家の歴史こそ、この京都名産「竹の子」の歴史でもありることはいうまでもありませんね。
5月5日は 子どもの日 ですが、その子どもが大きくなり、家を継ぎ、家の歴史や地域や文化の歴史を産みます。
竹の子のごとく すくすく育つ 子ども たちに このことを伝える記念日があるといいですね。
自称 たけのこ大使 莞鳴