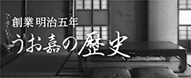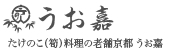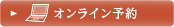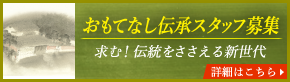春が終わる音を聞いた日
2025年 05月 24日
春が終わる音を聞いた日
――竹の子料理屋「うお嘉」、しばしの休業によせて
竹林の奥から吹く春の風は、どこか湿り気を含んでいて、土の中に眠っていた何かをそっと起こす気配がある。
それはたけのこかもしれないし、私の記憶そのものだったのかもしれない。
令和七年五月二十五日、私は五代目として務めてきた「うお嘉」の火を、ひとまず落とすことにした。
明治から百年以上にわたって続いてきた竹の子料理屋である。
京都・洛西の小さな山裾で、代々「旬」を信じてきた家業だった。
祖父と父の背中を見て育ち、春が近づくと魚の仕入れの準備より先に天候や竹林農家の堀り具合を確かめるのが、いつの間にか私の日常になっていた。
「竹の子は土からでよる、そやさけぇ 花の咲く具合でわかる。土筆や草花と一緒にでよるんや。」
祖父がそう言っていたように、自然の天候は全ての生き物に等しく、その恵みを与える。土の中は目には見えないが、その恵みに木々や草花は連動している。そして、人も等しくあると思い信じていた、
ただ、人間社会は近ごろ違うようだ。少しづつ、少しづつ、その連動から外れてったように思える。
実際、日本社会は変貌している。
飲食サービス業界の人手は減り、物流は高騰し、食材そのものが手に入らなくなり、生産供給が中止されることも伝統的食ほど増えている。
それらを乗り越えるために代替品や加工や工夫もしたが、もっと本質的な問題が、ひたひたと迫っていた気がする。
それは、「季節」や「風土」というものに対する、人々の感受性の鈍化だった。
誰もが「変わらなきゃいけない」と言い、
グローバル化やSDGsという“正しさ”を疑わずに受け入れていく流れの中で、
私たちのような“風土に耳をすます商い”は、次第に声を失っていった。
本来「持続可能性」とは、地域の知恵と自然との対話を続けることだったのではないか。
けれど、いつの間にかそれは「数字で測れること」や「国際基準に合うこと」へとすり替わっていった。
たけのこは、毎年同じように顔を出すわけじゃない。
風の向き、雨の量、朝晩の寒暖、すべてが揃って初めて、風土から“答え”が返ってくる。
それはAIの予測や、スマホのレシピ検索には映らない「人の感性の世界」だ。
私は、それを信じて料理をしてきた。
そして、その揺らぎこそが、日本の文化を支えてきたと思っている。
ある日、厨房で鍋の火を落としたとき、ふと心の中でこう呟いた。
「ええこの春の時は、もう戻らんのやろな」
それは、味覚の話だけじゃない。
日本人の感性そのものが、静かに沈んでいく音のひびきへの、私なりの別れの言葉だった。
最近、芥川賞を受賞した若い作家の小説を読むたびに、そうした喪失の空気を感じる。
私たちが忘れてしまった何かが、登場人物の沈黙の中に確かに息づいている。
そして、それは料理屋としての私自身にもあったのだと気づかされる。
それでも、もし誰かの記憶の中に、
竹林の青い匂いや、湯気の向こうに漂う木の芽の香りが残っているのなら、
「うお嘉」の春はまだ終わっていない。
そう思いたい。
文化は、インスタ映えの派手な動画、言葉や制度で残るものではない。
それは、ふとしたときに蘇る「香り」や「舌ざわり」や「記憶の感触」なのだ。
最後に、この場を借りて、これまで「うお嘉」を支えてくださったすべての方々に、心より御礼申し上げたい。
皆様の感性と味覚が、私たちの料理を意味あるものにしてくれました。
合掌。
令和七年五月二十五日
小松莞鳴