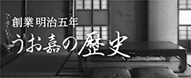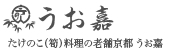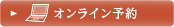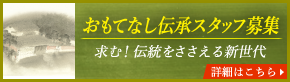たけのこ黙示録
2025年 05月 18日
たけのこ黙示録
数年前に亡くなった親父が、よくこぼしていた言葉がある。
「砂地の竹林から採れるたけのこは美味しくない。世間様は、たけのこはどれも同じだと思っている。色味が白ければ白いほど(値段が)高い。でもな、竹林がどんな土質を持っているかで、たけのこの味は全然違ってくるんや。
なのに、売っているほうも買っているほうも、見た目ばかりを重視して値段をつけたがる。だから、本当に美味しいたけのこを選ぶ力が、だんだんなくなってきておる。そして、味わう力も、どんどんどんどん落ちてきてる。」
長年にわたり、子どもの頃からたけのこを知る男が語る、説得力のある言葉だった。
確かに、見た目は同じように見えても、竹やぶの生産場所や土質によって、たけのこの味や固さ(繊維質)は大きく異なる。同じ生産者であっても、竹やぶの場所が違えば、すべてが異なるのだ。たけのこは、千差万別の素材なのである——親父はそう言い残していた。
京都の洛西(乙訓)と呼ばれるエリアでも、それぞれの細かな地域ごとに、たけのこの質は異なる。奥海印寺、小塩、上里、塚原(大枝)、物集女などは、昔から良質なたけのこが採れる土地である。
美食家として知られる北大路魯山人も、このエリアのたけのこを絶賛しており、現地に赴いて味わうことを強く薦めていた。
近ごろは「山城」エリアのたけのこが、ものを知らぬ都会人には人気のようだが、山城地域は、親父の言うところの“砂地の多く含まれる竹林エリア”にあたる。もし魯山人が今も生きていれば、きっと亡き父と同様に、コメントするだろう。
かの先人たちの言葉が正しければ、
味覚に関しては、人間はおそらく退化しているのかもしれない。
私たちは常に、社会や科学は進歩していると信じ込んでいるが、本来、進化させるべき感性や、維持すべき感覚への意識が、ぼやけてしまっているように思える。
「美味しいたけのこの味がわからない」——それはつまり、「美味しさの記憶そのものが、失われつつある」のかもしれない。
「伝統」や「文化」を守ると言うけれど、
本当に守らなければならないのは、己の五感であり、
日本人としての“感受性”や“感性”なのではないか。
「日本人、日本人」とSNSで声高に叫ぶ、馬鹿の一つ覚えのような者も多いが、はたして彼らは、自分たちが本当の“日本人の本質”を知っているのだろうか?
それは、甚だ疑わしい。
夏目漱石や森鷗外は、「個人」というものを小説で深く掘り下げたが、あれは結局、西洋思想の押し売りのようなものではなかったか。
——「まぁ、そりゃおかしくもなるわな」
そんな魯山人のような声が、どこか耳にこだまする。
日本には、古来より“言葉”を神秘的に扱う文化がある。
「言霊」として、別格の存在とみなされてきた。
それは“秘する”ものであり、“おおっぴら”にするようなものではない。
「もののあはれ」とは、“無”を意味するものであって、形にすべきものではない。
こうして語っている僕自身も、すでに“もののあはれ”ではない。
単なる、哀れな現代人にすぎない。
そのことを、どうか忘れないでいただきたい。
日本人である皆様へ——
このことを、どうか心に留めておいていただきたい。
令和七年五月十八日
小松莞鳴